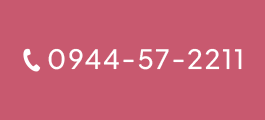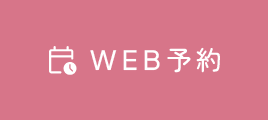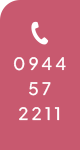呼吸器内科
このような症状はありませんか
- 咳が止まらない
- 咳が長引く
- 痰がからむ
- 息が切れしやすい
- 胸が痛む
- アレルギー体質がある
- 花粉症で悩んでいる
- いびきや寝ている際の無呼吸を指摘された
など
呼吸器内科とは

呼吸器内科は、鼻や喉、気管、気管支、肺、胸膜といった呼吸に関わる器官の疾患を診療する専門科です。診療対象となる疾患は幅広く、ウイルスや細菌による感染症、アレルギー疾患、悪性腫瘍、膠原病など多岐にわたります。
呼吸器のよくある疾患
気管支喘息
気管支喘息は、気管支に炎症が起こり、気道が狭くなったり過敏になったりすることで、呼吸困難や咳、痰が現れる病気です。多くの場合、アレルギーが関係していますが、運動や特定の薬剤でも同様の症状が引き起こされることがあります。
炎症が続くと気管支の粘膜が厚くなり、元に戻らなくなる可能性があります。このような不可逆的な変化が起こると、治療効果が低下し、日常的に呼吸困難や咳を感じるようになります。そのため、早期の診断と治療が極めて重要です。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)
COPDは、タバコの煙などの有害物質を長期間吸入することで気管支や肺に炎症が生じ、構造が破壊される疾患です。進行すると呼吸機能が低下し、慢性的な呼吸困難や咳などの症状が現れます。
壊れた肺胞は元には戻らないため、早期治療を開始して進行を遅らせることが重要です。初期段階では症状が分かりにくく、胸部レントゲンやCTで変化が確認できない場合もあります。呼吸機能検査が早期診断に有効です。
肺炎
肺炎は、肺にウイルスや細菌が感染することで発症します。特に免疫力が低下している高齢者や慢性疾患を持つ方は重症化しやすいため注意が必要です。発熱、激しい咳、痰、息苦しさ、胸痛などがみられる場合は、肺炎の可能性が考えられます。
気胸
気胸は、肺に穴が開いて空気が漏れ、肺と胸壁の間(胸腔)に空気が溜まる病気です。肺がしぼむことで胸痛や咳、息苦しさが生じます。
原因の多くは肺の表面にできたのう胞(ブラやブレブ)が破裂することによります。若い長身の痩せ形男性に多い傾向がありますが、高齢者ではCOPDや間質性肺炎などによる肺の脆弱化が原因となることがあります。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が停止したり低下したりする疾患です。ご家族や周囲の方から「いびきが大きく、時々呼吸が止まっている」と指摘されたことがある場合、この疾患の可能性が高いと考えられます。
夜間の睡眠が十分に取れないと、日中に強い眠気を感じ、学業や仕事の効率が低下するだけでなく、高血圧、糖尿病、心臓病、脳卒中などのリスクが大幅に上昇することが分かっています。そのため、早期に診断を受け、適切な治療を行うことが重要です。
自宅で簡単に実施できる検査(簡易PSG)もありますので、いびきに関する指摘を受けた方はぜひご検討ください。睡眠時無呼吸症候群の重症度に応じて、減量、横向きでの睡眠、マウスピースの使用、またはCPAP療法を提案しています。